![]()
 平成19年9月2日
平成19年9月2日
天保5年10月9日(1834年11月9日)〜慶応4年4月25日(1868年5月17日)
京都府京都市・壬生寺でお会いしました。
武蔵国多摩郡の農家に生まれ、江戸の天然理心流・近藤周助の養子となり、道場を継ぐ。
文久3年(1863年)の将軍・徳川家茂いえもち上洛に際し、警護のための浪士隊に参加して上京するが、そのまま京に残留。
京都守護職の配下で新撰組を組織し、のち隊長。
慶応3年(1867年)6月、見廻組頭取として幕臣となる。
翌年の3月、甲陽鎮撫隊を組織して新政府軍と戦う。(勝沼戦争)
ついで、下総国流山ながれやま戦争に参加したが、捕らわれ処刑された。
 |
近藤勇像 (京都市・壬生寺) (平成19年9月2日) |
壬生寺と新選組について
新選組は文久3年(1863)に、この壬生の地において結成された。
現在もその屯所跡が、壬生寺正門前の坊城通りに、二ヵ所残っている。
かつて壬生寺境内は、新選組隊士の兵法調練場に使われ、武芸や大砲おおづつの訓練が行われていた。
また新選組にまつわる逸話いつわも、当寺には数多く残っている。
壬生塚にある墓碑は、新選組やその遺族らによって建てられたものである。
近藤勇の胸像は、俳優の故・上田吉二郎氏が発起人となり、昭和46年に建立された。
胸像の左横の塔は、近藤勇の「遺髪塔」である。
また、毎年7月16日に池田屋騒動の日を卜ぼくし、「新選組隊士等慰霊供養祭」が行われる。
壬生塚に祀られている隊士
| 近藤勇こんどういさみ | 局長 | 没年 慶応4年(1868)4月25日 |
| 芹沢鴨せりざわかも | 局長 | 没年 文久3年(1863)9月18日 |
| 平山五郎ひらやまごろう | 副長助勤 | 没年 文久3年(1863)9月18日 |
| 河合耆三郎かわいきさぶろう | 勘定方 | 没年 慶応2年(1866)2月12日 |
| 阿比原栄三郎あびはらえいざぶろう | 副長助勤 | 没年 文久3年(1863)4月6日 |
| 田中伊織たなかいおり | 没年 文久3年(1863)9月13日 | |
| 野口健司のぐちけんじ | 副長助勤 | 没年 文久3年(1863)12月28日 |
| 奥沢栄助おくざわえいすけ | 伍長 | 没年 元治元年(1864)6月5日 |
| 安藤早太郎あんどうはやたろう | 副長助勤 | 没年 元治元年(1864)7月22日 |
| 新田革左右衛門にったかくざえもん | 平隊士 | 没年 元治元年(1864)7月22日 |
| 葛山武八郎かづらやまたけはちろう | 伍長 | 没年 元治元年(1864)9月6日 |
阿比原ほか7名の墓の左に刻まれた漢詩は、追悼の五言絶句で、左のように読める。
魂魄帰天地 此生奈有涯 定知泉下鬼 応是護皇基
(説明板より)
 |
胸像(右) 遺髪塔(左) (京都市・壬生寺) (平成19年9月2日) |
 |
誠 新選組顕彰碑 (京都市・壬生寺) (平成19年9月2日) |
碑文
局中法度書
一.士道ニ背キ間敷事
一.局ヲ脱スルヲ不許
一.勝手ニ金策致不可
一.勝手ニ訴訟取扱不可
一.私ノ闘争ヲ不許
右条々相背候者
切腹申付ベク候也
京都新選組同好会
結成20周年記念
皇紀2655年
平成7年3月13日
 |
壬生寺 (京都市中京区坊城通り仏光寺北入る) (平成19年9月2日) |
壬生寺 みぶでら
律宗に属し、本尊は地蔵菩薩立像(重要文化財)である。
寺伝によれば、正暦2年(991)三井寺みいでらの快賢僧都かいけんそうずにより創建され、古名を地蔵院、宝幢三昧寺ほうとうさんまいじなどと呼ばれていた。
その後、火災により堂宇を焼失したが、正元元年(1259)平政平たいらのまさひらにより復興され、さらに正安2年(1300)円覚えんかく上人が、仏の教えを無言劇に仕組んだ、壬生狂言(重要無形民俗文化財)を創始し大いに栄えた。
昭和37年に本堂が焼失したため、昭和45年に再建された。
また、境内北にある壬生狂言を演じる舞台、大念仏堂(重要文化財)は、安政3年(1856)の特異な構造物である。
当寺境内は、新選組が大砲や剣術・馬術の訓練をした場所として有名であり、壬生塚には近藤勇の胸像、芹沢鴨らの墓塔がある。
池田屋騒動があったと言われる7月16日には、毎年、慰霊供養祭が行われる。
京都市
(説明板より)
| 寺務所・朱印 受付時間 |
| 午前8時30分〜午後5時 |
| 新選組隊士遺跡 壬生塚 公開時間 |
| 午前8時30分〜午後4時30分 1人100円 |
| 壬生寺歴史資料室 公開時間 |
| 午前8時30分〜午後4時30分 大人200円 |
 |
新選組 壬生屯所遺蹟(八木邸) (京都市中京区坊城通四条南入西側) (平成19年9月2日) |
新選組発祥の地跡
ここは、幕末の頃、京都の浪士取締りや治安維持に活躍した新選組の宿所があったところである。
文久3年(1863)春、将軍家茂の上洛警護のため、清河八郎の率いる浪士組が入洛したが、その宿舎の一つとして使われたのが、当時壬生郷の郷士宅であった当屋敷であった。
浪士組は、在京20日余りで再び江戸に戻ったが、当所に分宿していた、芹沢鴨せりざわかも、新見錦にいみにしき、近藤勇、土方歳三ひじかたとしぞうらは、引き続き京都の警備のため残留し、京都守護職松平容保まつだいらかたもりの支配に属して「新選組」と名のった。
当初、新選組は、当屋敷に「新選組宿所」の標札を掲げ、隊員はわずか十数名で発足したが、次第に隊員が増加し、付近の農家にも分宿した。
以後、市中の治安維持に努め、元治元年(1864)の池田屋事件で一躍その名を轟かせた。
翌年の慶応元年(1865)4月、屯所は西本願寺に移された。
京都市
(説明板より)
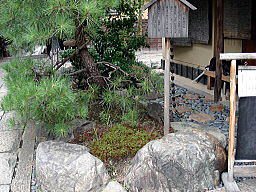 |
隊士腰掛の石 (京都市・八木家) (平成19年9月2日) |
隊士腰掛の石
こゝの石類は、本屋敷と表屋敷との間、つまり新選組の道場のあたりにあったものです。
隊士達も腰を下ろし、休んでいました。
屋敷内を二、三移動した後、ここに落ち着きました。
新選組発祥の地・八木邸
幕末、京の治安維持のために活躍した新選組は、文久3年(1863年)3月春、ここ洛西壬生村の八木源之烝(八木家11代目)宅にて誕生しました。
将軍家茂上洛の警護の名目で京に上った浪士隊のうち、八木家を宿所としていた芹沢鴨、近藤勇ら13名が、主張の相違から浪士隊と袂を分かち、京都守護職・松平容保のお預かりのもとに新鮮組を結成。
八木家長屋門の右柱に「松平肥後守御預新選組宿」の表札を掲げました。
八木為三郎翁(源之烝三男)の遺談によれば、「沖田総司だの、原田左之助なんかがその前へ立って、がやがや云いながら、しみじみ眺めて喜んでいた」といいます。
以来、壬生を拠点に白刃をもって不逞浪士鎮圧に奔走した彼らが、慶応元年(1865)、隊士の増員に伴い手狭となった壬生を引き払って西本願寺に屯所を移転するまでの3年間、初代局長・芹沢鴨らの暗殺をはじめ、池田屋の変、禁門の変など、新選組の激動の歴史が繰り広げられましたが、それらを時代とともに目撃してきたのがこの八木家です。
当家には、屯所の移転後も非番の隊士らが連れ立って遊びに来たり、明治維新後まで生き残った隊士が壬生の昔を偲んで訪ねてくることもありました。
| 芹沢 鴨 | 平山五郎 | 近藤 勇 | 土方歳三 | 新見 錦 | 平間重助 | 野口健司 |
| 沖田総司 | 山南敬助 | 永倉新八 | 原田左之助 | 藤堂平助 | 井上源三郎 |
(リーフレットより)
![]() (関連商品のご紹介)
(関連商品のご紹介)
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
