![]()
 平成15年6月26日
平成15年6月26日
文久2年12月26日(1863年2月14日)~大正2年(1913年)9月2日
東京都台東区谷中の旧居跡でお会いしました。
福井藩士の子。横浜生まれ。東大卒。
文部省に出仕し、大学時代の師フェノロサらと国内外に出張。
東京美術学校開設準備にあたり、明治23年(1890年)から同校校長をつとめました。
8年後、学内に天心排斥運動が起こり、辞職して日本美術院を創立しました。
この前後に中国、インドを旅行し、1904年からはボストン美術館勤務のため日米間を往復しています。
「東洋の理想」「日本の目覚め」「茶の本」をロンドン、ニューヨークから英文で出版して、東洋の優秀性を主張するとともに日本の役割を強調しました。
東京都指定旧跡 岡倉天心宅跡・旧前期日本美術院跡
指定 昭和27年11月3日
日本美術院は明治31年(1898)岡倉天心が中心になって「本邦美術の特性に基づきその維持開発を図る」ことを目的として創設された民間団体で、当初院長は天心、主幹は橋本雅邦、評議員には横山大観、下村観山らがいた。
活動は絵画が主で、従来の日本画の流派に反対し、洋画の手法を取りいれ、近代日本画に清新の気を与えた。
この場所に建てられた美術院は明治31年9月に竣工した木造二階建で、南館(絵画研究室)と北館(事務室・工芸研究室・書斎・集会室)からなり、附属建物も2,3あったといわれている。
明治39年(1906)12月に美術院が茨城県五浦[いずら]に移るまで、ここが活動の拠点になっていた。
昭和41年(1966)岡倉天心史跡記念六角堂が建てられ、堂内には平櫛田中作の天心坐像が安置されている。
平成11年3月31日 建設
東京都教育委員会
(案内説明板より)
訪問記
かなり小さな敷地でした。単なる小さな児童公園です。
公園内の六角堂の中に銅像があるんですが、金網とガラスでしっかり守られているので写真が撮りにくい!
ピンボケと手ブレで上手く写真が撮れませんでした。
う~ん、残念だぁ。
(平成15年6月26日訪問)
岡倉天心生誕の地 神奈川県横浜市の横浜開港記念会館のところに建っています。 (平成15年12月14日) |
岡倉天心碑
岡倉天心覚三は、文久2年(1862年)この地(当時の本町5丁目)にあった生糸売込商「石川屋」に生まれ、幼き日を横浜で送った。
明治23年、東京美術学校(現 東京芸術大学)を創立し、やがて校長になる。
その後日本美術院を結成、横山大観、下村観山、菱田春草などの日本画壇の偉才を育てた。
のちアメリカ、ボストン美術館の東洋部長となりアジア文化のため、活躍した。
(「横浜開港記念会館」のリーフレットより)
![]()
茨城県北茨城市大津町五浦の茨城大学五浦美術文化研究所・天心記念館でお会いしました。
 |
岡倉天心像 (茨城県北茨城市・茨城大学五浦美術文化研究所) 金箔・ブロンズ 昭和50年 平櫛田中 作 (平成18年9月28日再訪問) |
平櫛田中作《岡倉天心先生像》は、昭和6年12月に東京美術学校に設置された銅像の部分である。
天心没後20年目、生誕70年目という節目の年を目前にして完成した。
当時の美術学校長正木直彦らが建立を計画したとされるが、横山大観もおおいに関わっていた。
大観の強い勧めで平櫛田中が作者に指名されたが、大観は、天心のポーズを細かく指示した。
その平櫛が、長らく手元に置いた作品を茨城大学に寄贈した。
ブロンズに金箔を貼るというのは、仏式の様式であり、その背中には「釈天心」という戒名が記されていることから、平櫛にとってこの像が礼拝用だったことが想像される。
実際、平櫛は東京芸術大学で後進の指導に当たった際、登下校時には必ず自らの制作した肖像の前で深々と礼をしていたという。
(『岡倉天心と五浦』より)
 |
『五浦釣人ごほちょうじん』 (茨城県北茨城市・茨城大学五浦美術文化研究所) 平櫛田中 作 昭和37年 (平成18年9月28日再訪問) |
平櫛田中ひらくしでんちゅう作 『五浦釣人ごほちょうじん』
晩年の天心は、五浦海岸で好んで釣りを楽しんでいた。
田中はその釣人姿の天心像を多数制作している。
第一作は昭和5年の第17回院展で発表している。
本像は昭和37年、天心の生誕百年を記念して制作されたもので、一連の天心像の中で最大の作品である。
毛皮をまとい、右手に釣り竿を握り、左手に網を持つ姿は、ウォーナー博士撮影のスナップ写真をモデルにしたといわれている。
本像は、第48回院展に出品された後、本研究所に寄贈され、これがきっかけとなって天心記念館が建設された。
(説明板より)
| 天心の業績 |
近代日本を代表する文明批評家・美術史家、岡倉天心(本名覚三)は、1862年(文久2)横浜に生まれた。
幼少から英語を学び、東京大学入学後に教師のフェノロサの通訳をつとめるほど堪能だった。
卒業後18歳で文部省に勤務、奈良京都の古社寺を調査し、美術学校の設立に尽力するなど、明治政府の美術文化行政の確立にめざましい功績をあげ、27歳の若さで帝国博物館(現東京国立博物館)理事・美術部長、28歳で東京美術学校(現東京芸術大学)校長となった。
しかし、彼の指導方針に反発する派との対立から、1898年(明治31)に博物館、美術学校を相次いで辞職し、橋本雅邦、横山大観らと日本美術院を創立、野に下った。
以後、天心は、インドで詩人タゴールの一族と親交を結び、インド独立運動の青年たちに影響をおよぼす一方、アメリカのボストン美術館中国日本部長となり、英文著書『東洋の理想』『茶の本』を出版するなど、国際的に活躍の場を広げた。
(「茨城大学五浦美術文化研究所ガイドブック2」より)
茨城大学五浦美術文化研究所ご案内(案内板説明文から抜粋)
現五浦美術文化研究所の地所と建物は、1942年に天心の遺族米山高麗子氏より岡倉天心偉績顕彰会に寄贈され、1955年茨城大学に移管されました。
現在の研究所敷地内には、長屋門、旧天心邸(1904)、六角堂(1905)、天心偉績顕彰記念碑(1942)、ウォーナー像(1970)、天心記念館(1963)があります。
茨城大学では遺跡の保存に努力すると共に、岡倉天心と近代美術研究のために活用しています。
開館時間
午前9時30分~午後5時(入場は午後4時30分まで)
※11月~3月は
午前9時30分~4時30分(入場は午後4時まで)
休館日
毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)
年末年始12月29日~1月3日
 |
研究室(旧天心邸母屋) (茨城大学五浦美術文化研究所) ここには様々な客が訪れましたが、のちにフィラデルフィア美術館長、ボストン美術館東洋部長となるウォーナーはここに滞在して、天心の教えを受けています。 (平成16年5月30日) |
旧天心邸母屋
岡倉天心が五浦に土地を求めた2年後、明治38年に、自らの設計を平潟の棟梁小倉源蔵に託して建築したものである。
当初は62坪余であったが、明治40年には更に増築して大邸宅となった。
東側離室と西側奥の間は後に取り払われて、今は無い。
屋根は木羽葺であったが、保存のため昭和48年に、アスファルトパネルにかえた。
(説明板より)
 |
天心邸 (茨城大学五浦美術文化研究所) (平成18年9月28日再訪問) |
 |
天心邸 (茨城大学五浦美術文化研究所) (平成18年9月28日再訪問) |
天心邸
明治37年(1904)2月、自らの設計を平潟の棟梁小倉源蔵に託し、天心はボストンの美術館の仕事のためアメリカへと旅立った。
天心が五浦の地を手に入れた際には、鮑あわび料理の割烹観浦楼の建物がまだ残っていた。
仮の住居に使っていたその建物の木材を使ったらしく、新居は豪華ではないが、風雅な趣となった。
当初は62坪だったが、明治40年にさらに改築して拡張した。
天心没後、西側にあった12畳の書斎や東側の浴室など一部が撤去されている。
(新・説明板より)
 |
「亜細亜ハ一な里」の石碑 (茨城大学五浦美術文化研究所) (平成16年5月30日) |
『亜細亜ハ一な里』の石碑
天心が没して25年後、日中戦争が勃発した。
『東洋の理想』の冒頭の言葉「Asia is one」は大東亜共栄圏という戦争遂行の理念の一つとして利用され、一躍世に広まった。
そうした背景のもと、天心終焉の地・赤倉の土地保存のため、岡倉天心偉績顕彰会が昭和17年に設立された。
これを機に五浦の土地建物が顕彰会に寄贈され、この碑が建立された。
「亜細亜ハ一なり」の文字は横山大観が揮毫し、横顔の浮き彫りは美術院同人の新海竹蔵が制作した。
(説明板より)
六角堂
天心は、尊敬する中国の詩人杜甫の草堂に倣い、この小堂を六角形に設計した。
棟札には天心の自筆で「観瀾亭かんらんてい」(大波を観るあずまや)と書かれていた。
当初、内部は板の間で、炉が切ってあった。
眼前には広大な太平洋の海原が広がる。
天心はアメリカから帰ると、ここで瞑想し読書したほか、雨で沖に出られない日には窓から釣糸を垂らしたという。
(説明板より)
六角堂(観瀾亭)
六角堂の解体修理の際に、屋根裏から天心の自筆の棟札が発見された。
そこには、棟梁、平潟の大工小倉源蔵の名、明治38年の年記とともに「六角堂観瀾亭」と銘記されていた。
瀾とは大波のことで、「波を見るためのあずまや」という意味になる。
天心は、波に永遠性と絶え間ない変化を同時に認め、宇宙の本質と考えていた。
六角の形は、杜甫の草堂にならいながら、朱塗りと屋根の宝珠が仏堂をも表し、しつらえられた床の間には茶室のイメージも重ねられている。
天心は、ここで波を眺めながら瞑想にふけり、時に海に釣り糸を垂らしたという。
ノーベル賞詩人タゴールや北原白秋など、六角堂で天心をしのんだ文化人は多い。
(新・説明板より)
(平成18年9月28日再訪問)
 |
六角堂の内部 インドの詩人タゴール(ノーベル文学賞受賞者)は、大正5年に日本に訪れた時、ここに立ち寄り亡き友を偲んだといいます。 (平成16年5月30日) |
 「五浦岬公園」から見た六角堂
「五浦岬公園」から見た六角堂
 |
「日本美術院研究所跡」の碑 昭和45年3月建之 (平成16年5月30日) |
天心遺跡記念公園(日本美術院第一部五浦研究所跡)
ここは、岡倉天心(覚三)が、明治39年(1906)11月に、日本美術院を東京・谷中から五浦に移したとき、研究所(画塾)が建てられたところです
五浦時代は、大正2年(1913)9月に、天心がなくなるまでの数年間にすぎませんでしたが、大観、観山、春草らは、天心の教えをうけて研究にはげみ、すぐれた作品を今日に残しています
この地は、永い間荒れ地になっていましたが、近代日本美術史上かけがえのない遺跡として、観光資源保護財団が岡倉家から管理の委託を受けて、昭和53年から3年間かけて整備にあたり、昭和55年11月8日、新たに「天心遺跡記念公園」として一般に公開することになったものです
昭和57年3月1日 財団法人 日本ナショナルトラスト(旧財団法人 観光資源保護財団)
(説明石碑より)
 |
「筆塚」 (天心遺跡記念公園内) (平成16年5月30日) |
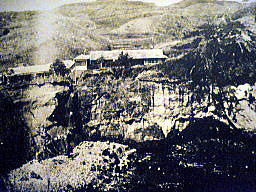 |
明治40年頃の日本美術研究所 (茨城大学五浦美術文化研究所・展示パネルより) (平成18年9月28日) |
 |
研究所画室で制作中の画家たち (茨城大学五浦美術文化研究所・展示パネルより) 手前より 木村武山、菱田春草、横山大観、下村観山 (平成18年9月28日) |
 |
茨城県天心記念五浦美術館 (茨城県北茨城市大津町椿2083) この美術館内に『岡倉天心記念室』があります。 (平成17年2月26日) |
岡倉天心記念室
(主な資料)
東京美術学校授業課題画
東京美術学校(現在の東京芸術大学)の授業で描いた課題画作品。
遺言状
天心が、亡くなる1年余前」、五浦でしたためた遺言状。
家族への財産分与を記したもの。
プリヤンバダ書簡
インドの女流詩人プリヤンバダから最晩年の天心に送られた書簡。
天心の書斎(推定復元)
天心が居住していた明治40年頃の姿を記念室内に再現
| 西暦 | 和暦 | 満年齢 | 事項 |
| 1862年 | 文久 2年 | 0歳 | 横浜に生れる |
| 1869年 | 明治 2年 | 7歳 | この頃ジェイムズ・バラーの塾で英語を学ぶ |
| 1875年 | 明治 8年 | 13歳 | 東京開成学校(のち東京大学と改称)に入学する |
| 1879年 | 明治12年 | 17歳 | 大岡もと(のち基子と称す)と結婚する |
| 1880年 | 明治13年 | 18歳 | 東京大学を卒業し、文部省に勤務する |
| 1886年 | 明治19年 | 24歳 | 欧米の美術行政視察にアーネスト・フェノロサらと共に出張する |
| 1889年 | 明治22年 | 27歳 | 東京美術学校が開校し、翌年校長となる |
| 1893年 | 明治26年 | 31歳 | 美術調査で初めて中国を旅行する |
| 1898年 | 明治31年 | 36歳 | 東京美術学校校長の職を退き、日本美術院を創立する |
| 1901年 | 明治34年 | 39歳 | インドに渡り、翌年にかけて仏跡等を巡る |
| 1902年 | 明治35年 | 40歳 | インドの詩聖タゴールと交流を深める 「東洋の理想」を執筆し、翌年ロンドンで刊行する |
| 1903年 | 明治36年 | 41歳 | 五浦に土地と家屋を求める |
| 1904年 | 明治37年 | 42歳 | アメリカのボストン美術館中国・日本美術部エキスパートになる 「日本の覚醒」をニューヨークで刊行する |
| 1905年 | 明治38年 | 43歳 | 五浦の別荘を新築し、六角堂を建てる ボストン美術館中国・日本美術部アドバイザーになる |
| 1906年 | 明治39年 | 44歳 | 赤倉に土地を求め家屋を建てる 日本美術院第一部(絵画)の五浦移転 大観、観山、春草、武山が同地に移り住む 「茶の本」をニューヨークで刊行する |
| 1907年 | 明治40年 | 45歳 | 仲秋観月の園遊会を五浦で開く |
| 1910年 | 明治43年 | 48歳 | ボストン美術館中国・日本美術部長になる |
| 1912年 | 明治45年 大正元年 |
50歳 | ボストン美術館の用務でアメリカへ渡る途中、インドに立ち寄る そこで女流詩人プリヤンバダ・デーヴィ・バネルジーと出会う |
| 1913年 | 大正 2年 | 51歳 | オペラ台本「白狐」を執筆後、病気のためアメリカより帰国する 古社寺保存会に出席 法隆寺金堂壁画の保存について建議案を作成する 療養のため新潟県の赤倉に移る 病状悪化し、歿す |
(岡倉天心記念室のリーフレットより)
茨城県天心記念五浦美術館の案内
開館時間:午前9時30分~午後5時
休館日:月曜日、12/29~1/1
入館料:所蔵品展=一般180円、企画展=企画展ごとに設定
交通:JR常磐線大津港駅下車、タクシーで約5分
(平成17年2月27日記)
 |
岡倉天心の墓 (平成16年5月30日) |
岡倉天心の墓地
この墓は日本美術院の主宰者岡倉天心の遺骨が、天心の辞世とされている和文の「我逝かば花な手向けそ浜千鳥 呼びかう声を印にて 落ち葉に深く埋めてよ 12万年明月の夜 弔い来ん人を松の影」およびAn Injunction(戒告)と題した英詩にもりこまれた遺志に沿い、天心没年の大正2年(1913)東京都の染井霊園の墓から、近代日本美術黎明の地五浦に分骨、埋葬されたものであり、歴史的・文化的に価値の高い史跡である。
平成元年7月24日 市指定
北茨城市教育委員会
(説明板より)
 |
岡倉天心の墓 (東京都豊島区・染井霊園) (平成22年2月9日) |
【岡倉天心の息子・岡倉古志郎】![]()
岡倉古志郎は東大の経済を出た国際政治学者で、岡倉天心の息子である。
『死の商人』や『財閥』などのタイトルで文庫や新書判のベストセラーを数多く書いた。
古志郎は、大倉喜八郎を「日本の死の商人」とし、「日清戦争では“石ころ缶詰”を納入して暴利をおさめ」て、「前線の将兵たちを怒らせ」「あくどい“死の商人”ぶりを発揮した」と断じた。
「石ころ缶詰」は、第二次世界大戦のあと、「戦争はもういや」という雰囲気が強かった時期は、とくによく活用された。
作家で評論家の木村毅きむらきは、「兵隊が戦地で配給された牛肉のカンヅメをあけてみたら、中に砂利がつまっていた」とし、「中味の腐ったカンヅメをおさめて、姫路師団の兵が・・・・・それを食って黒血を吐いたとか・・・・(水兵のはいていた靴は)糊ではっただけで、鋲を打ってないので、海水にぬれて、裏皮がはがれて、甲板からすべり落ちて溺死したとか、いろんなうわさが立った。それについて知りたかったら、木下尚江の小説『火の柱』をよむとよい」とまで書いている。
「私たちの少年時代は、大倉というと、同じ富豪仲間でも奸悪かんあくな、げすな奴だという印象を受けていた」とも書いている(『実業之日本』昭和27年2月15日号)。
つまり木村は、「小説を読んで事実を知れ」といっているのである。
編集、再刊ものを入れて、木村は生涯に、訳書、小説、評論、伝記等、200冊以上の本を出している。
「大倉高商』で教師をしていたこともあり、「日本文学振興会」から「菊池寛賞」も受けている人物である。
古志郎は「大倉財閥は“死の商人”“戦争成金”であり、やがては、中ソ両国への侵略戦争の張本人、ファシスト軍閥の鼓舞者となった」と主張した。
光文社からカッパブックスで出された『財閥』は、昭和30(1955)年度のベストセラー第11位となる。
岩波文庫から昭和26年(1951年)に発行され、翌年から岩波新書に入れられた『死の商人』は、昭和61年(1986年)まで増刷を重ねながら売れ続けた。
牛肉のかわりに馬肉を詰めることは、十分すぎるほどあったと思われるが、「砂利」を詰めることは、流れ作業ではむずかしいし、特定の相手に届く可能性はゼロである。
にもかかわらず、高名な学者や評論家まで、これが実在したものとして「石ころ缶詰」という言葉を用い、これを人身攻撃の材料として使った。
しかも世間はこれを信じて「なるほど」と納得してしまった。
経済学者からも歴史学者からも「石ころ缶詰」についての疑問はまったく出されなかった。
戦後に初めてこれを問題にしたのは、専門の研究者でも物書きでもない図書館の司書である。
中村道冏みちあきさんは、「大倉高等商業学校」が昇格してできた「東京経済大学」の図書館に勤務していたが、昭和33年(1958年)1月、同図書館の「月報」に、「永福石―石の缶詰はウソだったということ」を発表して、真相を訴えたのである。
(参考:砂川幸雄 著 『大倉喜八郎の豪快なる生涯』 草思社 2012年第1刷発行)
(令和2年1月13日 追記)
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
